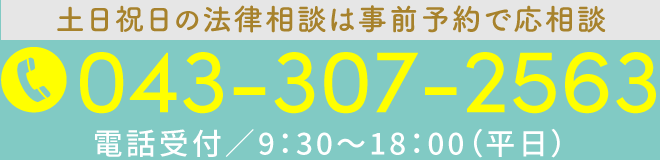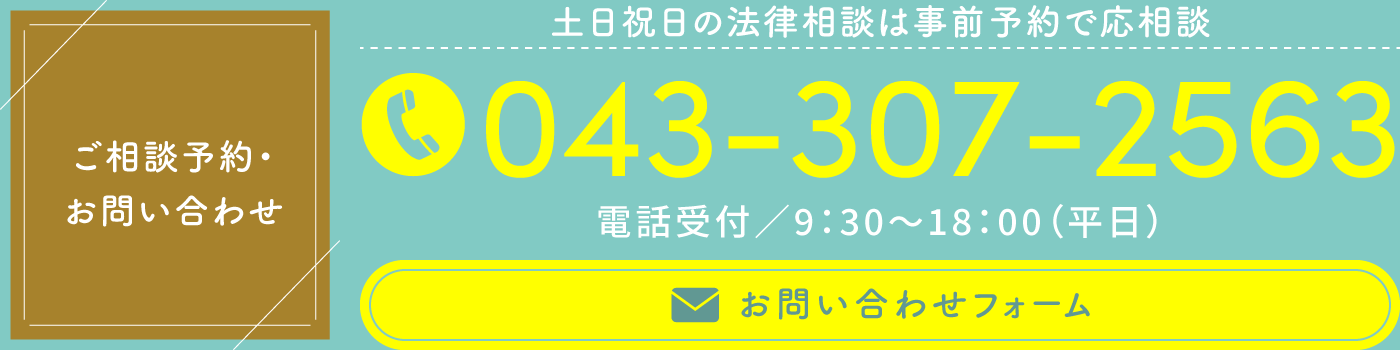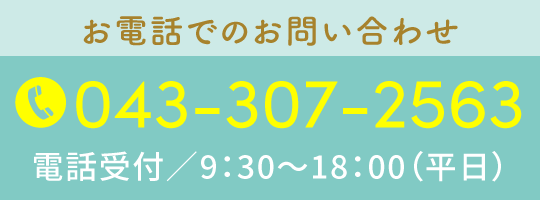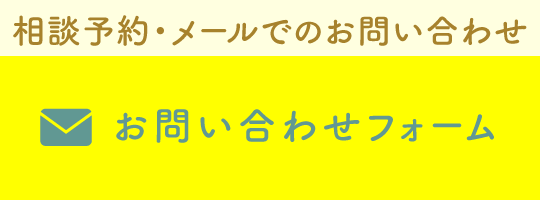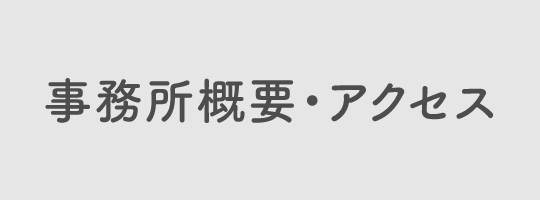このページの目次
無断転貸は「背信的行為」でなければ、契約解除は認められない
この記事では、無断転貸を理由とした明渡しを検討中の方に、明渡しが認められる場合について、解説を行います。
定型の賃貸借契約書のほとんどには、賃借権の譲渡と転貸を禁止する条項が設けられており、民法612条も賃借権譲渡と転貸を禁止しています。
これだけを見ると、無断転貸や賃借権の無断譲渡が行われた場合、即刻、賃貸借契約を解除できるようにも思えます。
しかしながら、判例は、無断転貸や賃借権譲渡が行われたとしても、「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合には、契約解除が認められないという判断を下しています(最高裁判所昭和30年9月22日判決など)。
以下では、無断転貸や賃借権譲渡を理由とした解除が認められる具体例を、判例(※)を交えながら紹介していきます(※最高裁判決以外は「裁判例」と記載すべきですが、単に「判例」と呼称します。以下、同様です。)。
転貸収入が発生している場合は解除が認められやすい
無断転貸の事例においては、賃借人から、利用形態に変更が無く、背信的行為にあたらないといった反論が行われることがあります。
しかし、賃借人が、賃貸人に隠れて転貸料と賃料の差額を利得していた場合、利用形態に変更が無くとも、判例は解除を認める傾向にあります。
転貸料と賃料の差額を利得していたことを指摘する近時の判例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 無断転貸された部分が物件の一部分であり、使用態様に変更が無く、転貸人も退去したケースにおいて、転貸により利益を得ていたことを指摘して契約解除を肯定したもの(東京地裁令和3年6月3日判決)
- 営業形態の変更を伴わない店舗の無断転貸について、倍の転貸料の支払があったことなどを指摘して契約解除を肯定したもの(東京地裁令和4年1月25日判決)
親族を無償で同居させた事例では、解除は否定される傾向にある
解除が認められにくい事件類型も存在します。その一つが、親族を無償で同居させたという事例です。
戦後間もない住宅事情がひっ迫した時期に、親族を無償で同居させたに過ぎない事例では、判例は、契約解除を否定する傾向にありました(東京高裁昭和28年2月9日判決など)。
個人事業主の法人成りの場合、解除は否定される傾向にある
解除が認められにくい事件類型の一つとして、賃借人の個人事業主が法人成りし、法人が賃借物件を利用継続したという事例が挙げられます。
例えば、最高裁昭和39年11月19日判決ではミシンの個人営業をしていた賃借人が、税金対策のために、法人を設立して個人事業主の頃と変わらない業務を継続していた事例において、契約解除が否定されました。
東京地裁平成18年1月18日判決では、ラーメン店を個人で営業していた賃借人が、法人成りして従前と同様のラーメン店の営業を継続していた事案において契約解除が否定されました。
契約解除が否定された事例では、使用態様に変更が無いことが指摘されています。法人成り後に、使用態様が変更された場合には、契約解除が認められやすくなるでしょう。
形式上、業務委託であっても、実質は無断転貸と判断されることがある
賃借人が、業務委託契約という名目にて、賃借中の物件を第三者に使用させている場合も、実質は無断転貸と評価されることがあります。
以下の事情がいくつか重なると、名目上、業務委託契約であっても、第三者への無断転貸と評価されることがあります。具体的な判断は弁護士に相談した方が良いでしょう。
- 業務委託料が固定額となっている
- 賃借物件使用中の第三者が、業務委託ではなく、賃貸という認識を持っている
- 第三者に委託した業務について、賃借人が、売上、経費等を把握していない
- 賃借人が、業務委託先への業務上の指示や、報告事項の聴取を行っていない
- 店舗内の設備・什器備品は、業務委託先が独自に調達している
- 敷金と評価し得る金員の授受がある
- 営業に必要な許認可を業務委託先が取得している
- 光熱費は、業務委託先が負担している
委託の実質が、無断転貸とされ、「背信的行為」と認められれば、解除できる
賃借人と第三者の業務委託が無断転貸と判断され、無断転貸が背信的行為と評価されると、契約解除は肯定されます。
無断転貸とされた業務委託について、契約解除を認めた判例の具体例として、東京地裁平成7年8月28日判決(美容院の業務委託)、東京地裁令和3年11月29日判決(女性用ウィッグ販売の業務委託)などが挙げられます。
業務委託名目の無断転貸についても、上述のとおり、賃借人が転貸料を利得していれば、背信的行為として評価される傾向にあります。
一方、営業委託ならば賃貸人が承諾済みとの誤った説明を聞いて、賃借を開始し、当初から第三者にラーメン店営業を委託したなどの事情がある事案について、転貸利益の発生が無いこと等も考慮し、無断転貸による契約解除を否定した判例があります(東京地裁平成25年3月7日判決)。
また、古い判例で、「のれん分け」のための試用として飲食店の営業を委託し、賃貸人の苦情申し入れ後直ちに営業委託を中止した事例において、無断転貸による契約解除を否定した判例もあります(東京地裁昭和61年10月31日判決)。
株式譲渡や役員変更などを理由とした解除には、賃貸借契約書上の特約が必要
賃借人が中小零細企業の場合、形式上、法人格に変化が無くとも、株式(持分)譲渡や役員変更が行われてしまうと、経営実態が変更されてしまう危険があります。
現に、賃貸人側が、株式(持分)譲渡や役員変更が賃借権の無断譲渡であるとして契約解除を主張するケースがあります。
しかし、最高裁平成8年10月14日判決では、賃借人が小規模で閉鎖的な有限会社における持分譲渡・役員交代は民法612条で禁止される賃借権譲渡に該当しないとされています。
この判例によると、株式(持分)譲渡や役員変更を理由に契約を解除するには、無断で役員や資本構成を変動させたときは契約を解除できる旨の特約を設ける必要があります。
ただし、特約を設ければ、100%解除できるわけではありません。特約に反した株式(持分)譲渡や役員変更により、賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊する程度に至っている必要があります。
例えば、株式(持分)譲渡に多額の対価の授受がある、利用態様に変更が生じた、賃料が歩合制で組織変更により賃料の多寡に影響が生じる、組織変更に際して賃貸人に嘘を述べた、賃貸人への報告を怠った、組織変更以外にも法令に違反した業務を行ったなど不信行為があった、などの事情が重なるほど、契約解除は認められやすくなります。
まとめ
無断転貸・賃借権の無断譲渡による契約解除が認められるか否かは、難しい法的判断を伴います。家賃保証会社のサポートを得にくい問題でもあります。
オーナー様ご自身だけで解決することは難しいかもしれません。無断転貸・賃借権の無断譲渡で、お困りの方は、オーブ法律事務所への相談予約をご検討ください。
※2023年1月執筆当時の情報を前提としたものです。
本記事の記載内容に関して当事務所・所属弁護士が何らかの表明保証を行うものではなく、閲覧者が記載内容を利用した結果について何ら責任を負いません。